認知症の徘徊とは?その原因と症状
「まさか、ここまで遠くに行ってしまうなんて…」
それは、私がケアマネジャーをしていた頃の出来事です。
土曜日の午後、ご本人と同居していた長男さんとその奥様が在宅中、ふとした瞬間にご本人がいないことに気づきました。以前から近所のコンビニへ買い物に行くことがあったため、「また少し歩いてすぐ戻ってくるだろう」と思い、しばらく様子を見ていたそうです。
しかし、時間が経っても戻らず、不安が募る中、17時頃に警察へ捜索願を提出した。
その日は事業所も休みで、家族だけでの対応を強いられた中、19時頃ようやく警察から連絡がありました。
ご本人は遠く離れた市で発見されたとのこと――
ホッとしたのも束の間、ご本人は途中で転倒しており、救急車に乗車をしたそう。搬送先の病院で警察に通報されたようです。
この出来事から、徘徊のリスクが想像以上に大きいことがわかります。
本記事では認知症の徘徊でどんなリスクがあるかにフォーカスして介護者ができる具体的な対策と地域支援の活用法について、ケアマネジャーとしての視点から詳しくお伝えします。
徘徊の定義と高齢者における影響
徘徊とは、目的や理由が明確でないままに歩き回る行動のことを指します。高齢者、特に認知症を患っている方に多く見られる症状の一つです。安全なはずの自宅や施設を抜け出し、見知らぬ場所へと歩き続けてしまうことがあり、重大な事故や行方不明といったリスクを伴います。
認知症と徘徊の関係
認知症には記憶障害や判断力の低下、時間や場所の感覚の喪失などが含まれます。これらが原因となり、「買い物に行くつもりが目的を忘れて道に迷った」「自宅へ帰るつもりが逆方向へ進んでしまった」といった状況が起こるのです。
徘徊による主なリスク
1. 事故やケガの危険
- 道路に飛び出して交通事故に遭う
- 転倒による骨折
- 段差や階段からの転落
- 暑さ・寒さによる熱中症・低体温症などの身体的ダメージ
2. 行方不明による命の危険
- 遠くまで歩いて帰れなくなる
- 発見が遅れると脱水症状、衰弱、最悪の場合は命を落とす可能性もある
→ 実際に、認知症による行方不明で死亡に至る事例も報告されています
3. 第三者とのトラブル
- 店舗や他人の家に入り込み「窃盗」などと誤解される
- 通報や警察沙汰になることで、本人や家族の精神的負担が大きくなる
4. 家族・介護者への負担
- 精神的なストレス・罪悪感
- 常に見守らなければというプレッシャー
- 結果的に介護疲れやうつ状態につながることも
高齢者の徘徊防止対策|「閉じ込める」より「見守る」工夫を
毎日の介護の中で、「もう鍵をかけて出られなくすればいいのでは?」と感じる方もいるかもしれません。
しかしその方法、法律に触れる可能性があります。今回は、“閉じ込める徘徊対策”のリスクと、“見守る”ための実践的な対策についてお伝えします。
「うち鍵」はなぜ危険?法に触れる可能性のある行為
以下のような行為は、場合によって法律に触れることがあります。
- 監禁罪(刑法220条)
- 高齢者虐待防止法
- 人権侵害・人格権の侵害
閉じ込める意図が明確で、本人の自由を制限しすぎると「身体拘束」と見なされるリスクがあります。
なぜ「補助錠」は法に触れにくいのか?
補助錠の使用が違法と判断されにくいのは、以下のような理由からです。
- 「完全な拘束」とは見なされにくいため
補助錠は、あくまで予防策として設置されるものであり、見守り体制と併用されることが前提となっています。完全に家から出られなくするような強い拘束とは異なり、状況に応じて解除できることが多いため、「監禁」とは判断されにくい傾向があります。 - 「身体拘束」ではなく、「環境整備」と捉えられるため
徘徊による事故を未然に防ぐために、安全確保を目的として設置された補助錠は、介護の一環としての「環境整備」と見なされやすく、適切なケアとして受け止められることが多いです。 - 見守り機器やGPSとの併用が前提となっているため
アラームやセンサー、GPS端末などと組み合わせて使われるケースが多く、「本人の安全を見守る仕組みの一部」として活用されています。そのため、本人の自由を完全に奪うものではなく、人権侵害にもあたらないとされやすいのです。
つまり、簡単に解除可能な構造で、完全に閉じ込めるものではないこと、そして見守りやGPSといった機器と併用し、本人の安全と気持ちの両方に配慮されていることが重要です。
こうした視点を持って選ぶことで、家族にとっても、本人にとっても納得感のある徘徊対策が可能になります。
おすすめの徘徊対策グッズ
✔ センサー付き玄関アラーム
玄関が開くと音が鳴る仕組み。家族が気づきやすいです。
✔ GPS機能付き靴・見守り端末
位置情報が把握できることで、行方不明時の早期発見に有効。
✔ 携帯電話の活用
通話での確認や位置検索ができるが、常に持ち歩く習慣がある方に有効。
✔ 地域との連携
ご近所の方にあらかじめ状況を伝えておくと、外に出た際の声かけや通報につながります。
徘徊グッズを利用例
私が担当していた利用者さんのご家族で、セコムから出ているGPS付き端末を常に身につけていました。
携帯電話のGPS機能を入れ本人の位置を確認していたご家族もいました。
ただし、常に持ち歩くわけではないため、「必ず安心」とは言い切れない側面もあります。持ち歩くのを忘れてしまった方はいて、探せず苦労していた方もいらっしゃいました。
在宅サービスや日中の活動も大切
デイサービスなどを活用し、日中の活動量や生活リズムを整えることで、夜間の徘徊を減らす効果もあります。
しかし人によっては、疲れていても動き出してしまうことも…。
「絶対に止められる方法」はないからこそ、複数の対策を組み合わせた“見守り”が大切です。介護保険で貸与できるものもありますので担当のケアマネジャーにもご相談ください。
地域との連携と支援制度
地域包括支援センターの役割
地域包括支援センターは、介護に関する相談窓口です。お住まいの包括支援センターはご存じですか?徘徊への不安や、対策方法のアドバイス、必要な福祉サービスの紹介など、幅広くサポートしてくれます。ケアマネジャーがいても包括支援センターに声をかけておく必要はあると思います。
自治体の徘徊防止サービス
多くの自治体では、認知症高齢者の見守り支援を行っており、GPSの低額料金での貸出制度や見守りネットワークへの登録制度を設けています。事前に登録しておくことで、万が一の時にも素早く情報が共有されます。ケアマネジャーから情報提供を受けるのが早いかもしれません。もし把握していないことがあったら、自治体で発行している冊子などを活用するのもオススメです。
地域ネットワークの実態
「認知症サポーター」や「見守り隊」といった地域のボランティア団体の活動は地域により様々です。実際には私自身、それらを積極的に活用した経験はあまりありません。これは、ボランティア団体の活動の熱量や体制にも左右される部分があると感じています。ただ認知症で困っている家族同士の集まりなどを主催しているボランティアグループなどがあるので情報交換会などを実施しているところもあります。
またご近所で理解のある方と、家族の状況や様子について軽く情報共有できるような関係性を築いておく方が、現実的で安心感があると感じることもあります。日常の中で「少し気にかけてもらう」程度の関わりでも、徘徊時の早期発見につながります。
とはいえ、やはり一番頼りになるのは地域包括支援センターの存在です。専門的な視点とネットワークを持ち合わせており、地域資源をうまくつなげてくれる役割を担ってくれる点で、非常に心強いと感じます。
徘徊におけるサポート
医療機関での相談と連携
認知症による徘徊が見られたら、まずは医療機関で相談しましょう。薬の調整や精神的ケアなど、医師のアドバイスを受けることで対処の幅が広がります。
医師による認知症診断の重要性
認知症の種類や進行度を把握することで、適切な介護や環境整備が可能になります。専門医による診断を受けることは、介護者にとっても安心材料になります。
伴走型サポートの効果
医師・看護師・ケアマネジャーなどがチームで支える「伴走型支援」は、長期的に安定したケアを実現する鍵となります。地域との連携がその土台となります。
介護施設の提案
徘徊は、ご本人でも止めることができないかなり大変な認知症状の一つです。それを家族だけで抱え込むのは大変です。
私からの提案は、老人保健施設の入所、近隣施設のショートステイなど施設での見守りです。
家族の負担は増すばかり。休む時間はないと思います。ご自分の用事もしなければなりません。施設入所なんてかわいそう・・・と思うかもしれませんが、徘徊して交通事故に遭ったらご本人もご家族も運転している人も皆が不幸です。
施設入所することで、全てが安全というわけではないですが、プロの見守りの目があることでご家族にとっての束の間の休息となります。
まとめ|徘徊を「防ぐ」より「支える」視点で向き合おう
認知症による徘徊は、決して特別なことではなく、多くのご家族が直面する可能性のある課題です。
大切なのは、「閉じ込める」のではなく、「見守る」「支える」視点で、本人の尊厳や安全に配慮しながら対策を講じることです。
この記事では、徘徊のリスクや原因に加え、
- 法律に触れにくい補助錠の工夫
- GPSやセンサーを活用した見守り
- 在宅・施設サービスとの併用
- 地域包括支援センターや医療との連携
- 近隣住民やボランティアとのつながりの持ち方
など、さまざまな角度から「安心をつくる」具体策をご紹介しました。
完璧な対策はなくても、複数の手段を組み合わせることで、ご本人もご家族も少しずつ心にゆとりを持つことができます。
「一人で抱え込まず、使える支援を活用する」ことは、決して弱さではありません。
安心と安全を守るために、今できる一歩を踏み出していきましょう。

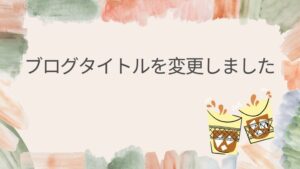
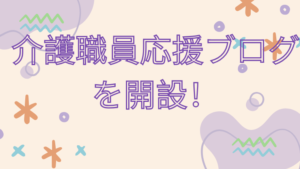
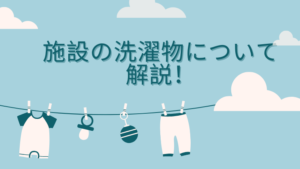
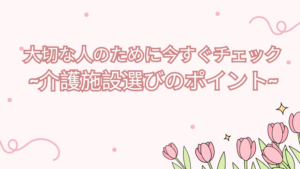
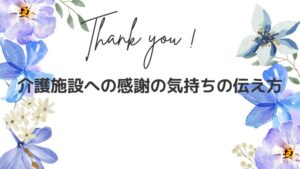
コメント