訪問介護で掃除してもらえる!って思っていませんか?
あってはならないのですがケアマネジャー自身も訪問介護の掃除などの制度のしばりが厳しいので、たまに誤った知識を家族にお伝えしてしまうこともあります。
このブログでは、訪問介護の「できること」と「できないこと」は、利用する個人によって変わることを解説していきます。
もし担当ケアマネジャーが誤った知識を伝えた際は、このブログを通して疑問を投げかけてみましょう。
結論として訪問介護の生活援助の「できないこと」4つを挙げていきますね。
| できないこと | 例 |
|---|---|
| ①本人以外への援助 | 家族の食事づくり・洗濯・来客対応 |
| ②日常生活の援助ではないこと | 草むしり・水やり・ペットの世話 |
| ③日常の家事ではないこと | 大掃除・模様替え・家具の移動 |
| ④同居家族がいること | 家族が家事を担えると判断される |
自分の親、もしくは自分自身に当てはめて読み進めてもらえたら幸いです。
早速、訪問介護の「できること」「できないこと」を一緒に確認していきましょう。
「できること」と「できないこと」で整理する訪問介護サービス
40歳以上の国民の税金で成り立っている介護保険。
訪問介護で全てできるよ〜と社会全体で判断していたら、税金負担は今以上にあると思います。今の税金負担で成り立っているのは「できること」と「できないこと」をしっかり区別しているからです。
この項目では、「できること」と「できないこと」を整理していきます。
「できること」から見る訪問介護のサービス
訪問介護っていうのは、ヘルパーが自宅を訪問して介護をしてくれることです。
大きく2つに分られます。
| 区分 | 内容の例 |
|---|---|
| 身体介護 | 入浴、排せつ、食事など |
| 生活援助 | 調理、洗濯、掃除など |
案外できることも幅広く、ご本人の「困りごと」を解決することが可能です。
ただ、介護保険上では本人の困っていることから本当に必要なサービスを洗い出して行くので、今伝えた全てのサービスは使えません…。
介護保険の制度では「自立した生活を送る」ってのが大前提にあるから、仕方ないんです。
訪問介護の制度上3つの「できないこと」
訪問介護の「できないこと」は、大きく3つに分けられます。
「え?4つじゃないの?」と思った方もいるかもしれませんが、実は制度上は3つに整理されているのです。
① 本人以外への援助はNG
(例:同居家族の食事づくり・洗濯・買い物、来客の応接、自家用車の洗車など)
② 日常生活の援助以外はNG
(例:草むしり、花木の水やり、ペットの世話など)
③ 日常の家事を超えることはNG
(例:家具の移動や修理、大掃除や窓拭き、園芸や特別料理など)
以上3つを見て気づいたと思いますが、本人以外の家族や日常を超える援助はできませんよってことなんです。
同居家族の有無で変わる訪問介護の使い方
ここでは、さらに利用できない最後の1つについて解説します。
掃除や洗濯、買い物などは同居家族がいると、基本的には使えないのです。
詳しく説明していきますね。
同居家族がいても使える場合
基本的に掃除などサービスが利用できる人は「家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な人」に限られているんですよ・・。なかなかハードルが高いです。
本当に必要でサービスをしないと生死が・・っていうことなら、ケアマネジャーが行政に直接掃除が必要なんですと交渉する必要も出てきます。
まさにケアマネジャーの聞き取り力や行政へのプレゼン力が試されるところです。
一人暮らしの場合に利用できる幅
一人暮らしなら概ね利用できます。先ほども言ったように介護保険では「自立した生活を送る」のが前提になるので、全て使うというと難しい場合もあります。
一人暮らしでも制度だけではカバーしきれない場面がありますよね。
そんなときに選ばれているのが、自費で利用できる訪問介護サービスです。
ケアプランに作成の時のポイント
先ほども話したように、しばり(制度の制約)が多いのが介護保険。
40歳以上の方の血税なので仕方ありません。それでも使用しないと生活が・・・という方は、ケアマネジャーへ困りごととして気持ちをぶつけてみましょう。
サービス内容の判断は「本人の生活状況+家族構成」で決まり!
例えば・・・
「本人が一人暮らしで足が悪くてトイレや自室の掃除ができなくて不衛生」
「うつ病の息子がいて足の踏み場のない家で本人も認知症で掃除ができなくて住める状況じゃない」
このような内容ですとケアプランで位置付けることができます。
ケアプランの内容をしっかり確認しよう
ケアプラン(介護サービス計画書)に必要な内容がきちんと入っているか、必ず確認しましょう。これは家族や本人の大切な役割です。
ケアマネジャーも人間ですから、抜けや漏れがあることもあります。確認の場として「サービス担当者会議」がありますので、ケアプランの「サービス内容」に希望が反映されているか自分の目で見てみましょう。
まとめ
ここでは訪問介護の生活援助で「できること」「できないこと」について解説しました。
訪問介護の生活援助「できないこと」4つ
生活援助でできないことを4つ挙げました!
| できないこと | 例 |
|---|---|
| ①本人以外への援助 | 家族の食事づくり・洗濯・来客対応 |
| ②日常生活の援助ではないこと | 草むしり・水やり・ペットの世話 |
| ③日常の家事ではないこと | 大掃除・模様替え・家具の移動 |
| ④同居家族がいること | 家族が家事を担えると判断される |
同居家族の有無で使えるサービスの幅が大きく変わる
訪問介護の生活援助は、同居家族がいるかいないかで大きく左右されます。
国の基準では、同居家族が障害や疾病などで家事を担えないと認められる場合に限り、生活援助の利用が可能です。
最終的にはお住まいの市町村によって判断が異なることもあるため、ケアマネジャーに確認してみてください。
ケアマネジャーとの連携
最後に大切なのは、ケアマネジャーとの連携です。確認すべきポイントは2つあります。
- 掃除などのサービスが必要であることをしっかり伝えること
- ケアプランにきちんと組み込まれていること
この2点を必ずケアマネジャーと確認してみてください。
以上で解説は終わりです。
「うちの場合はどうだろう?」と思ったら、遠慮せずケアマネジャーに聞いてみてください。きっと生活に合わせた答えが見つかるはずです。




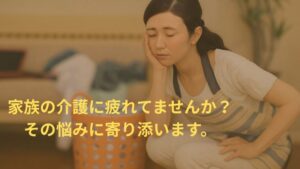


コメント